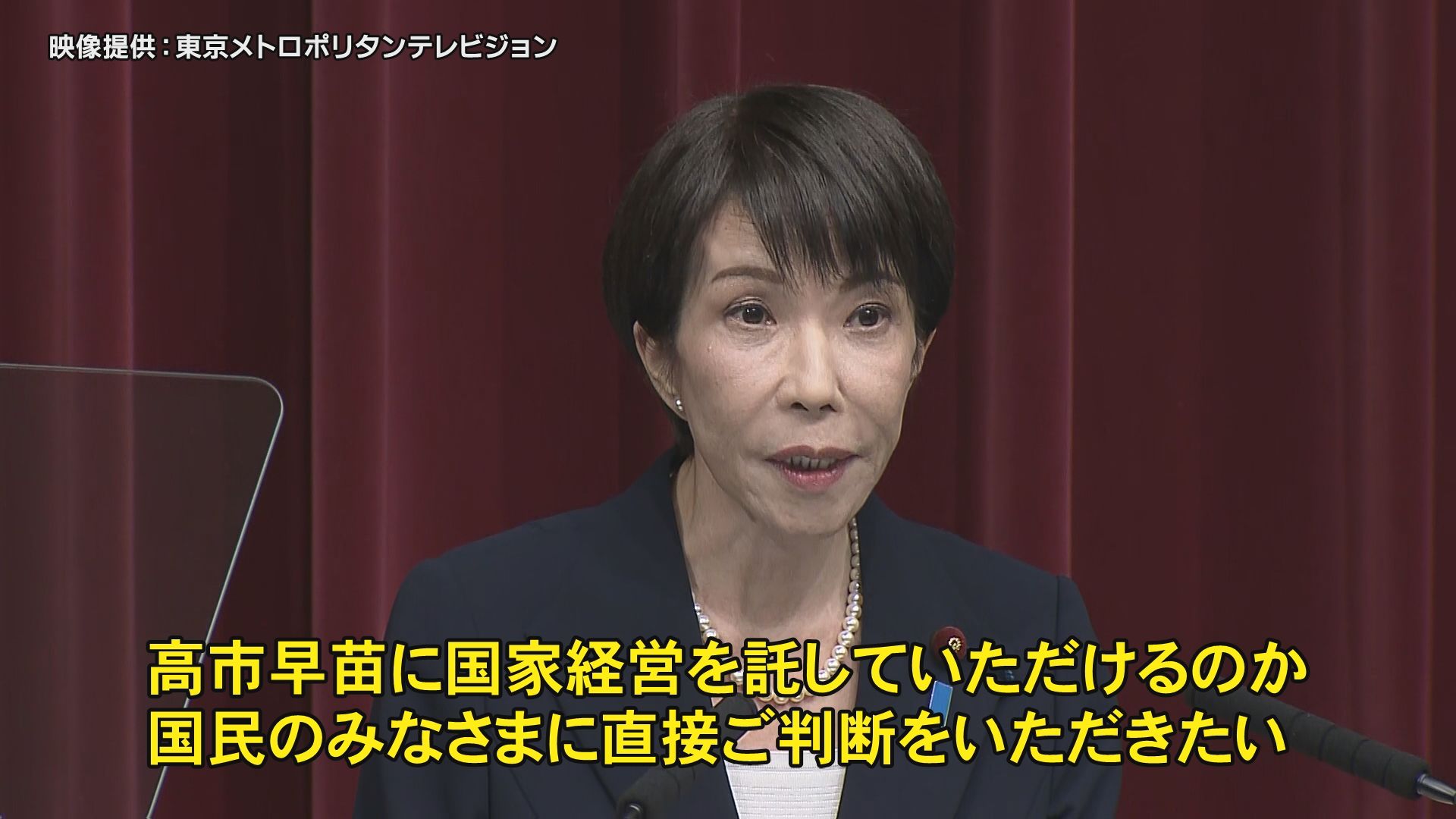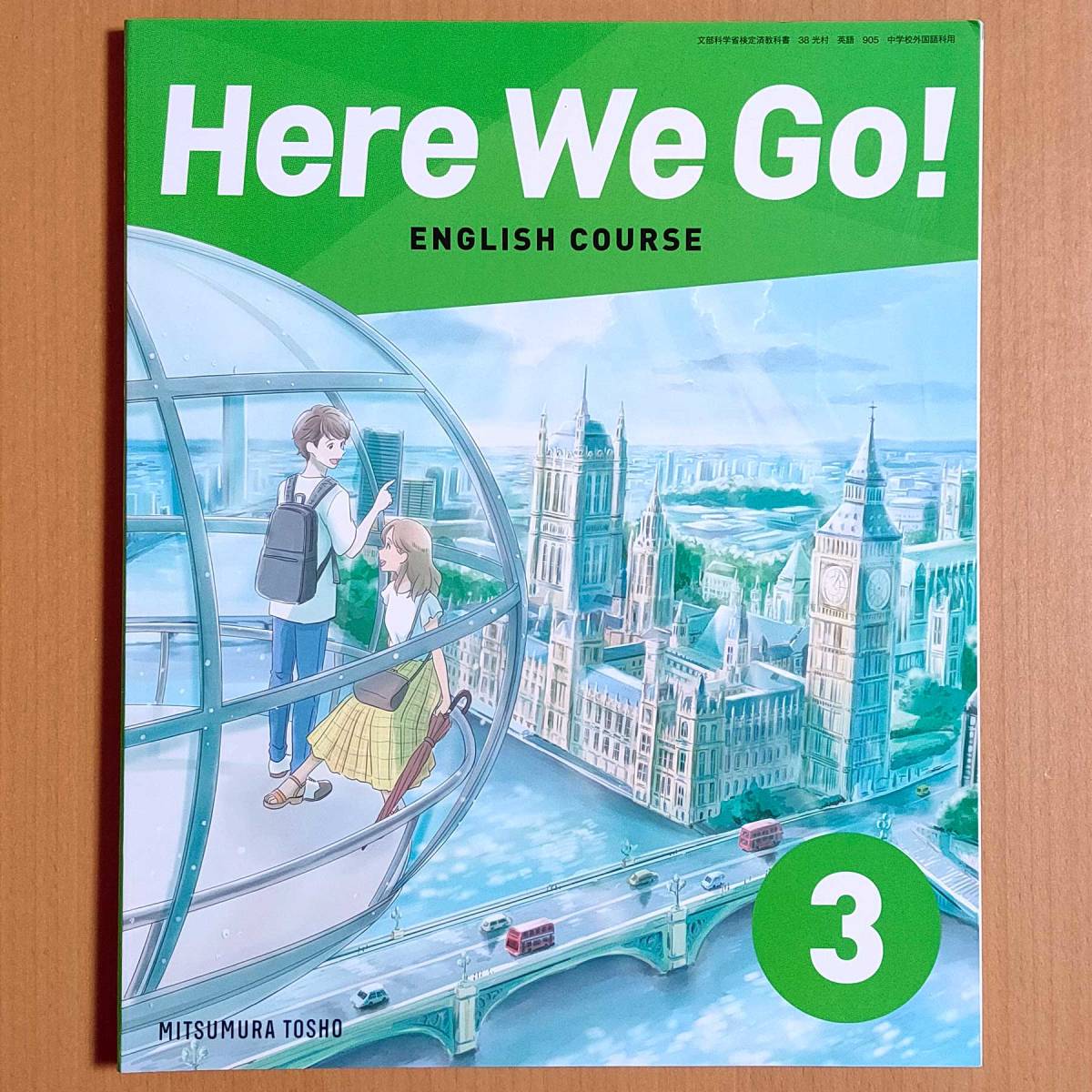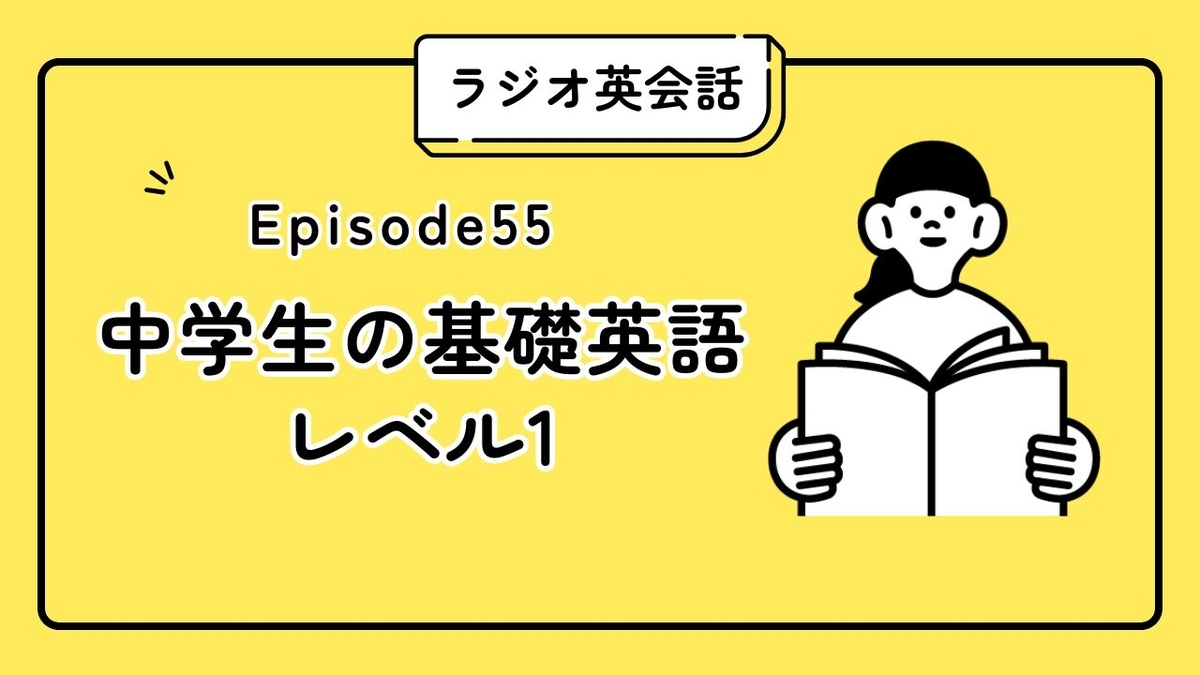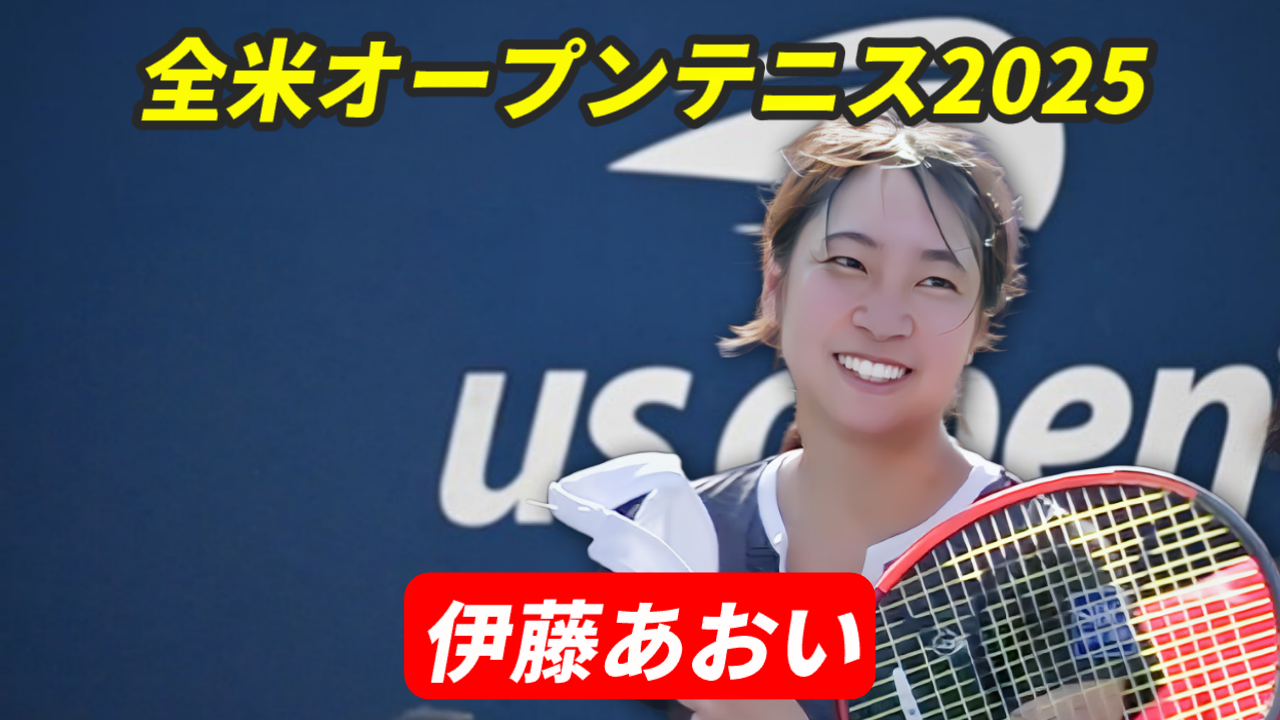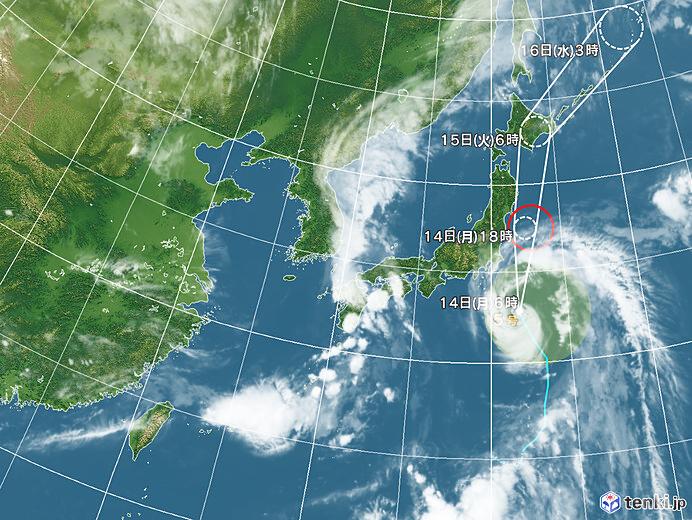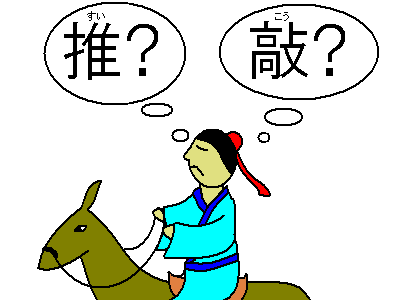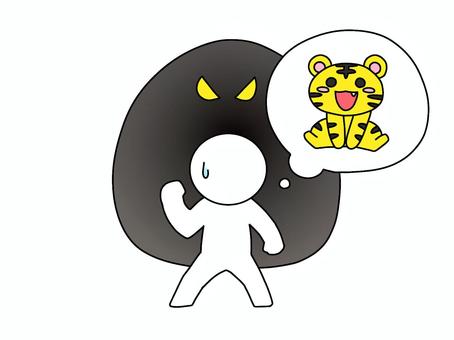三顧の礼(さんこのれい)
<故事の概要>
「三顧の礼」は、中国の『三国志』に登場する故事です。時は後漢末期、天下統一を目指す劉備(りゅうび)が、天下の情勢を見通す天才的な軍師として名高い諸葛亮(しょかつりょう)を軍に迎え入れるために、彼の住む隆中(りゅうちゅう)に三度も足を運んで説得したという逸話に基づいています。一度目と二度目は諸葛亮に会えず、三度目にようやく対面がかない、その熱意に心を動かされた諸葛亮は劉備の軍師になることを承諾しました。この時の諸葛亮の作戦が、後に「天下三分の計」として知られるものとなります。
<慣用句の意味>
「三顧の礼」は、優れた才能を持つ人物を、敬意を払い、誠意を尽くして何度も訪ねて招くことを意味します。単に何度も訪問するだけでなく、相手への深い尊敬の念や、どうしても力を借りたいという強い熱意が込められています。
<補足>
この故事は、主君と家臣の理想的な関係性を示すものとして、後世に語り継がれてきました。劉備の諸葛亮に対する敬意は、ただの「人材スカウト」ではなく、「人としての誠実なつながり」を大切にしたものであったことが強調されます。
<使用例>
・「社長は、新しいプロジェクトの責任者として彼を招くため、三顧の礼を尽くした。」
・「あの会社は、優秀なエンジニアを獲得するために、まるで三顧の礼のような熱意を注いでいる。」
<類義語>
「礼を尽くす」 や 「頭を下げる」 などが意味として近いですが、「三顧の礼」は特に 「何度も訪れる」「才能ある人物を招く」 というニュアンスが含まれています。
<関連する記事>
<関連する画像>
<関連する動画>
Visited 71 times, 1 visit(s) today