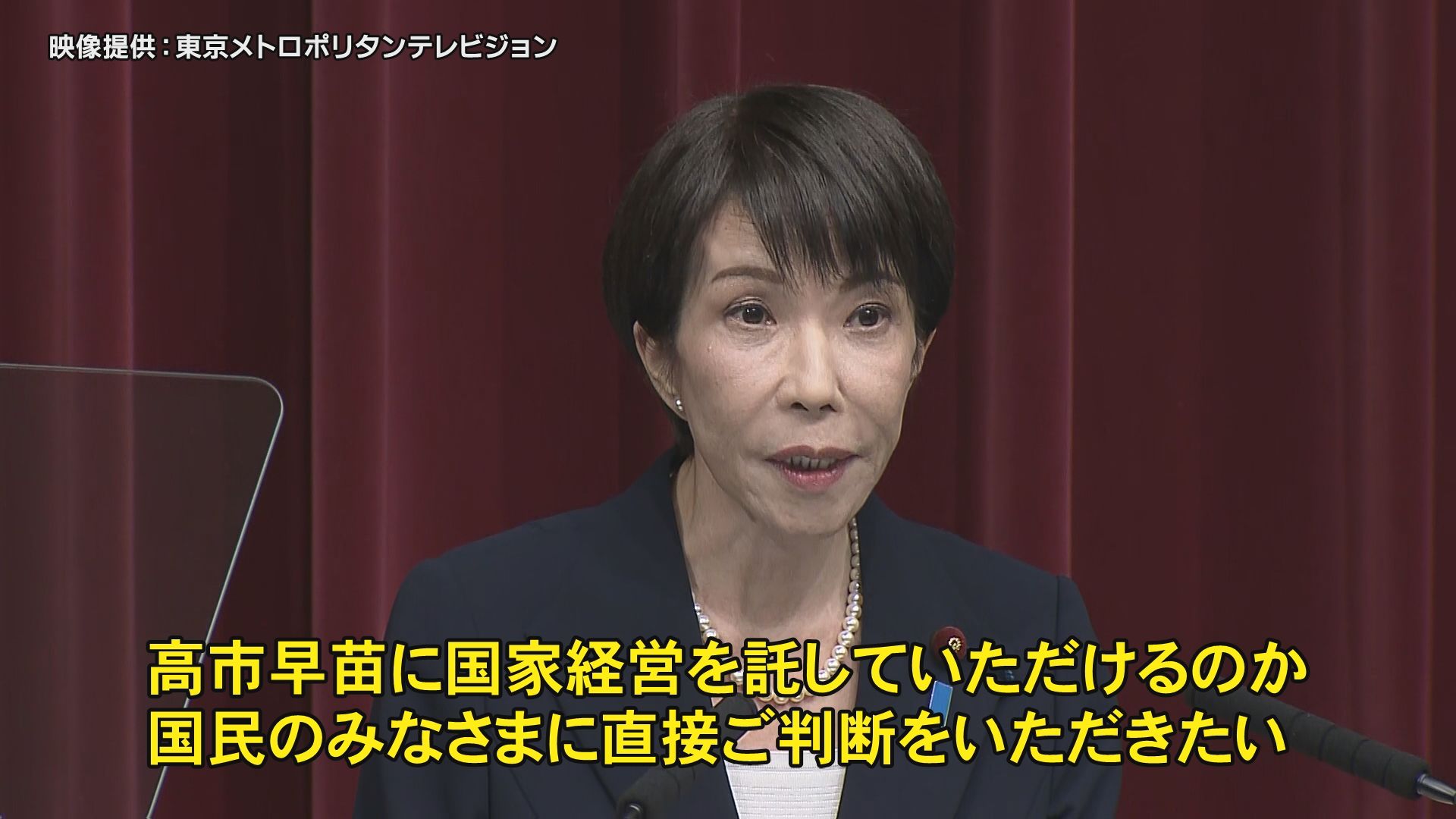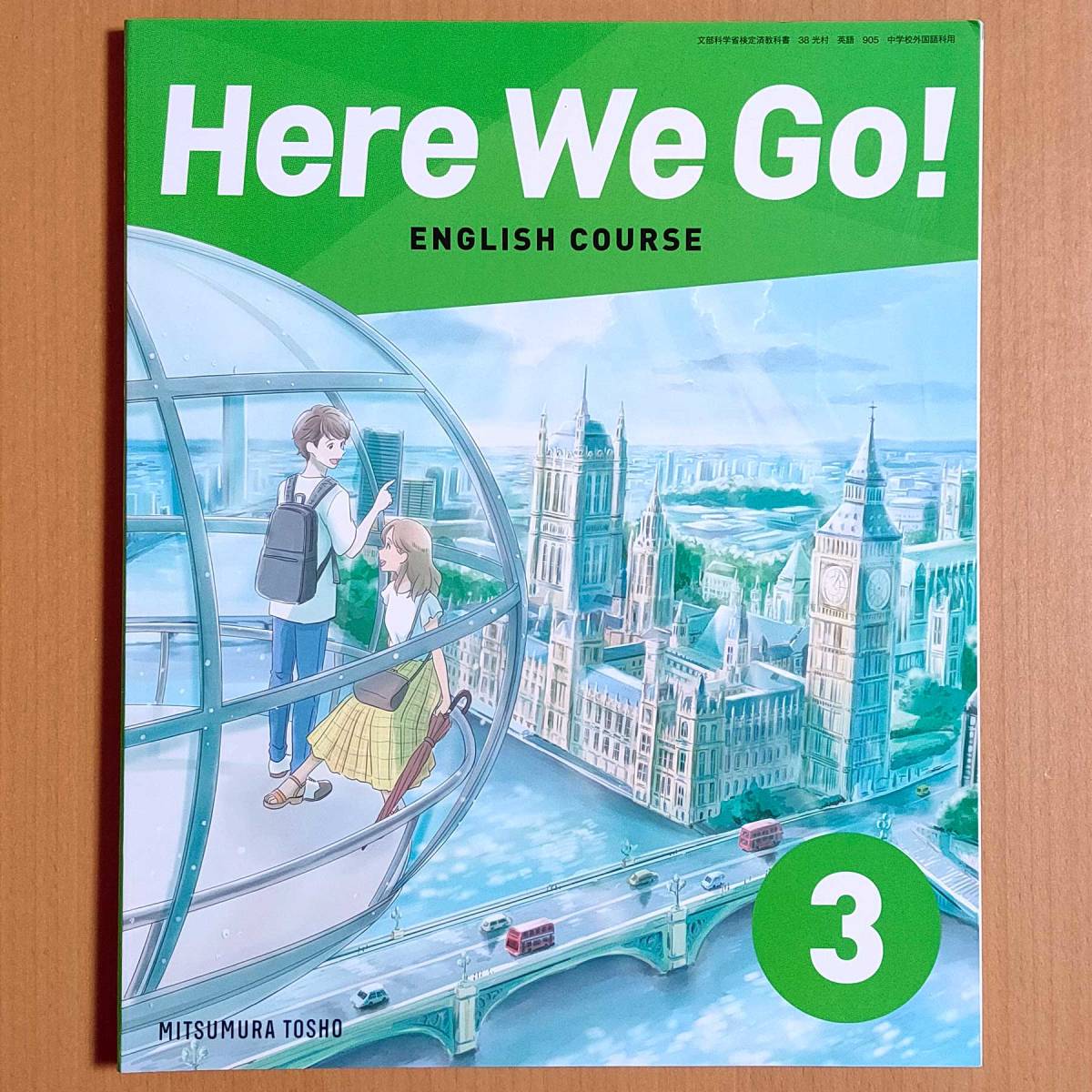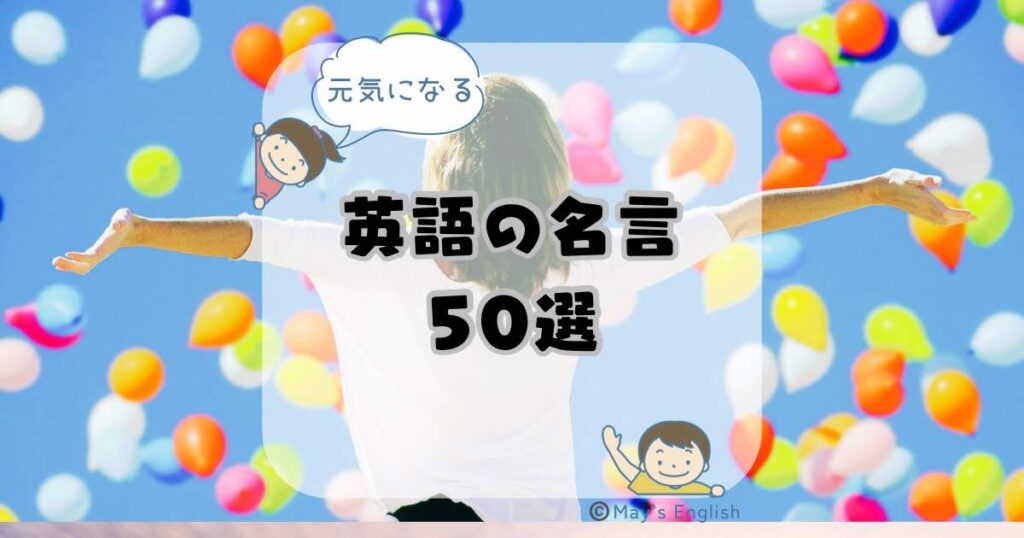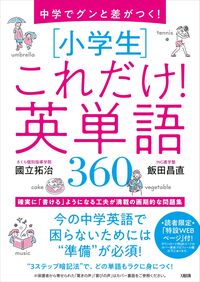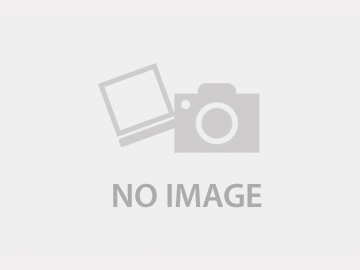<終わらない辞書作りの旅、NHKドラマが完結>
2025年8月19日、NHK総合のドラマ10枠で放送された『舟を編む~私、辞書つくります~』が全10話の放送を終えました。三浦しをんさんの名作小説『舟を編む』を原作に、新入社員・岸辺みどり(池田エライザ)の視点で描かれたこのドラマは、放送開始前から注目を集めていましたが、最終回を迎えた今、視聴者から大きな反響を呼んでいます。私自身、原作の大ファンとしてこのドラマに心から魅了され、毎週火曜の夜が楽しみで仕方ありませんでした。今回は、私の感想とともに、視聴者の声や過去の映画版の再評価も交えて、この作品の魅力を振り返ります。
<原作の魂を継ぐ、現代的なアプローチのドラマ>
私が『舟を編む』に惹かれた理由は、辞書という一見地味な存在の裏に隠された、作り手の情熱と執念です。誰もが手に取ったことのある分厚い辞書、その一語一語には、編集者たちの想像を超える努力が詰まっています。原作では、言葉への探求心が先輩から後輩へと受け継がれ、終わりなき辞書作りの世界が描かれていました。特に、薄くて透けない辞書の紙を作るメーカーのエピソードは、細部にまでこだわる職人魂に心を動かされました。このドラマは、そんな原作の精神をしっかりと受け継ぎつつ、現代的な視点で新たな魅力を加えています。ドラマでは、原作の主人公・馬締光也(野田洋次郎)ではなく、岸辺みどりの視点で物語が展開。ファッション誌から異動してきたみどりが、辞書編集部の個性的な面々に翻弄されながらも、言葉の魅力に目覚めていく姿が丁寧に描かれました。特に、新型コロナウイルスの影響で世界が一変する中、辞書編集部が直面する課題や、馬締の問いかけがもたらす衝撃は、現代社会とリンクする深いテーマでした。視聴者からも、「言葉は誰かを傷つけるためではなく、誰かを守り、誰かとつながるためにある」というメッセージが心に響いたとの声が多く聞かれます。
<視聴者の声:言葉の力を再認識させる名作>
放送終了後、XなどのSNSでは、ドラマの感動を語る投稿が溢れています。たとえば、ある視聴者は、「岸辺さんが用例カードに『取り残さない』『一緒に行こう』と語りかけるシーンで涙が止まらなかった。言葉一つひとつが大切にされていると感じた」と感動を綴っていました。 また、別の投稿では、「辞書作りという地味な題材なのに、セリフがスペクタクルに溢れ、ピュアな恋愛ドラマとしても楽しめた」と、ドラマの意外な魅力に驚く声も。特に、辞書編集部のメンバーが失敗を前向きに捉える姿勢や、共に働く仲間との絆に感動したという意見が多く見られました。「一緒に頑張ってきた人たちと喜びを分かち合える素晴らしさを感じた」との投稿は、ドラマが描く人間関係の温かさを象徴しています。 また、「姿勢を正して見なければならないドラマ。言葉を大事にする心が伝わってくる」と、作品の丁寧な作りに敬意を表す声も。 池田エライザの演技も高く評価されており、「岸辺みどり役のエライザさんに惚れた!」という熱いファンの声も目立ちました。さらに、ドラマの影響で原作や辞書そのものに興味を持った視聴者も多いようです。「このドラマを観て、初めて国語辞典の奥深さに気づいた。日本語を再認識できた」とのコメントや、関連番組「ケンボー先生と山田先生~辞書に人生を捧げた二人の男~」への期待も寄せられています。 これらの声から、ドラマが言葉の大切さやものづくりの喜びを広く伝え、視聴者に深い感動を与えたことがわかります。
<映画版『舟を編む』の再評価>
ドラマの成功を受けて、2013年に公開された映画版『舟を編む』(監督:石井裕也、主演:松田龍平、宮崎あおい)も再び注目を集めています。映画は原作の主人公・馬締光也の視点で描かれ、辞書編集の緻密なプロセスと、彼の不器用ながらも真っ直ぐな生き様が丁寧に表現されていました。当時も高い評価を受けた作品ですが、ドラマの放送終了後、Xでは「ドラマを観て映画も観てみたけど、どちらも素晴らしい!」といった声が上がっています。映画版は、ドラマとは異なる静謐な雰囲気と、馬締と香具矢(宮崎あおい)の恋愛模様が特に評価されています。「映画の馬締の不器用さが愛おしかった。ドラマとはまた違う角度で辞書作りの情熱が伝わってきた」との投稿もあり、両者の違いを楽しみながら、原作の多面性を再発見する視聴者が増えているようです。ドラマの現代的なアプローチに対し、映画はより内省的で文学的な味わいが特徴。原作ファンの私としては、どちらも原作の魂をしっかりと受け継いでいると感じます。
<私の感想:期待を超えたドラマの完成度>
私がこのドラマに期待していたのは、原作の「言葉への敬意」と「作り手の情熱」をどう映像化するかでした。結果として、その期待は見事に超えられました。岸辺みどりの視点で描くことで、辞書作りの世界が初心者にもわかりやすく、かつ新鮮に映りました。特に、編集部の個性的な面々(矢本悠馬や柄本時生の演技が光る!)とみどりの成長が織りなす人間ドラマは、毎話心を揺さぶるものでした。また、原作で印象的だった「辞書の紙」のエピソードも、ドラマで丁寧に描かれていたのが嬉しかったです。薄くて透けない紙を作る職人たちのこだわりは、辞書作りの細部への愛を象徴するもの。このシーンを見ながら、改めてものづくりの尊さを感じました。最終回では、コロナ禍という現代の課題を織り交ぜつつ、「大渡海」の完成に向けた編集部員たちの奮闘が感動的に描かれ、涙なしには見られませんでした。
<これからの『舟を編む』:言葉のバトンを未来へ>
『舟を編む~私、辞書つくります~』は、単なるドラマを超えて、言葉の力や人と人との繋がりを再認識させる作品でした。放送終了後も、Xでは「このドラマは史に残る名作」「辞書を手に取るたびにこの物語を思い出す」といった声が飛び交い、視聴者の心に深い余韻を残しています。 また、ドラマの成功が映画版の再評価にも繋がり、原作、映画、ドラマそれぞれの魅力を比較しながら楽しむファンが増えているのも嬉しい現象です。私自身、原作のファンとして、このドラマが新たな視点で『舟を編む』の世界を広げてくれたことに感謝しています。言葉は、時代や環境が変わっても、誰かを守り、誰かとつながるためのもの。このメッセージが、ドラマを通じて多くの人に届いたことを願います。もしまだドラマを観ていない方、原作を読んでいない方、映画を観ていない方がいたら、ぜひこの機会に触れてみてください。
出来たら原作を読んでいただきたい。久しぶりに文学作品に触れたような余韻が残る作品だと筆者は感じた一冊です。
<関連する記事>
<関連する画像>
<ツイッターの反応>