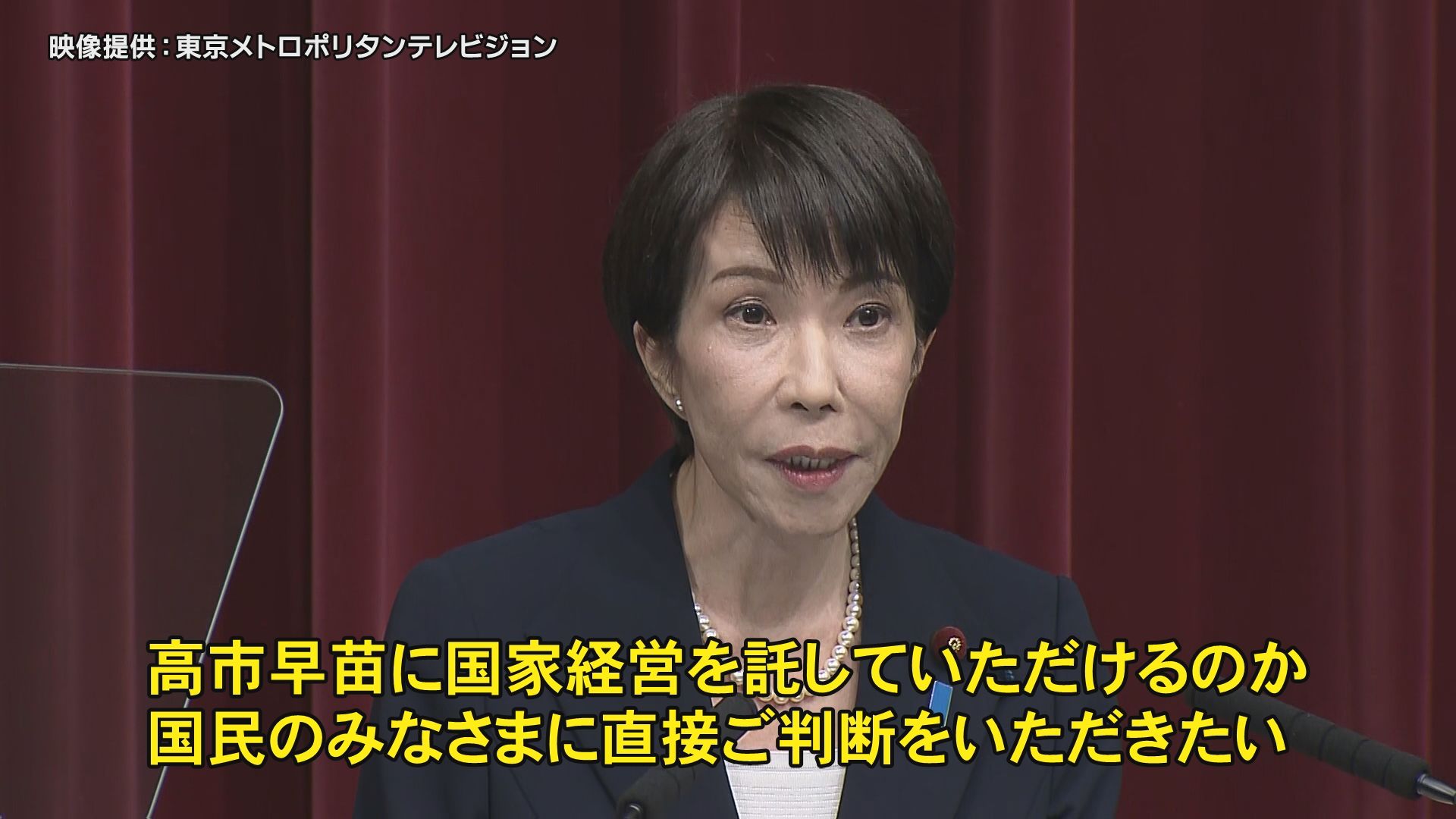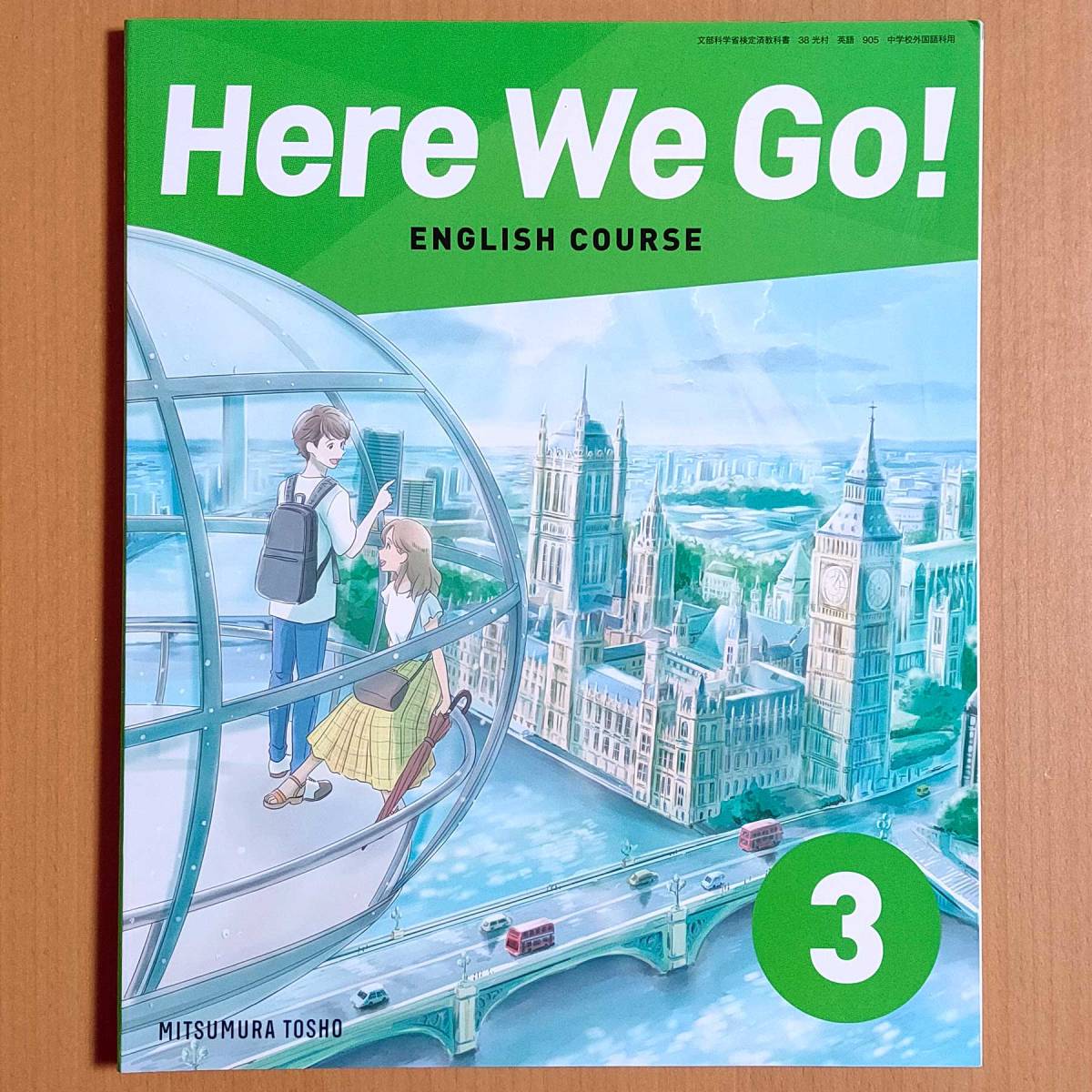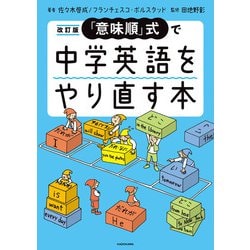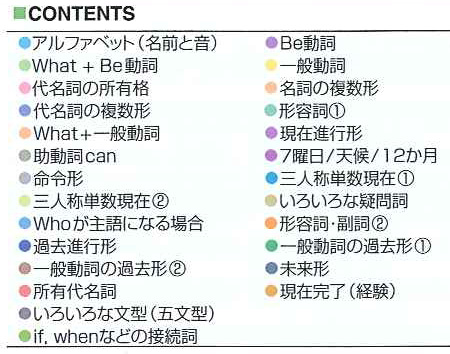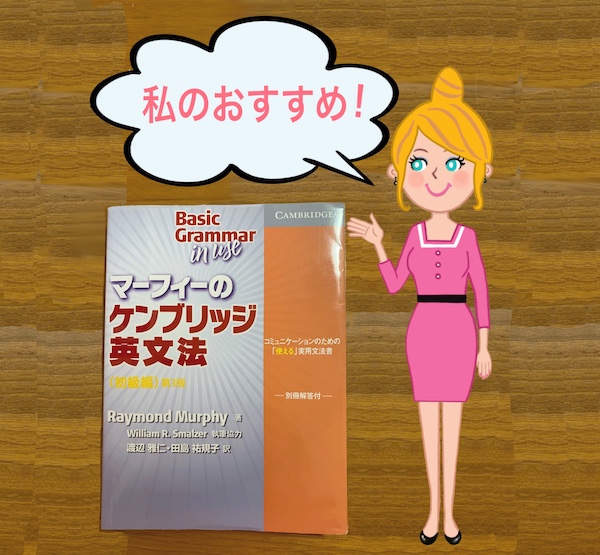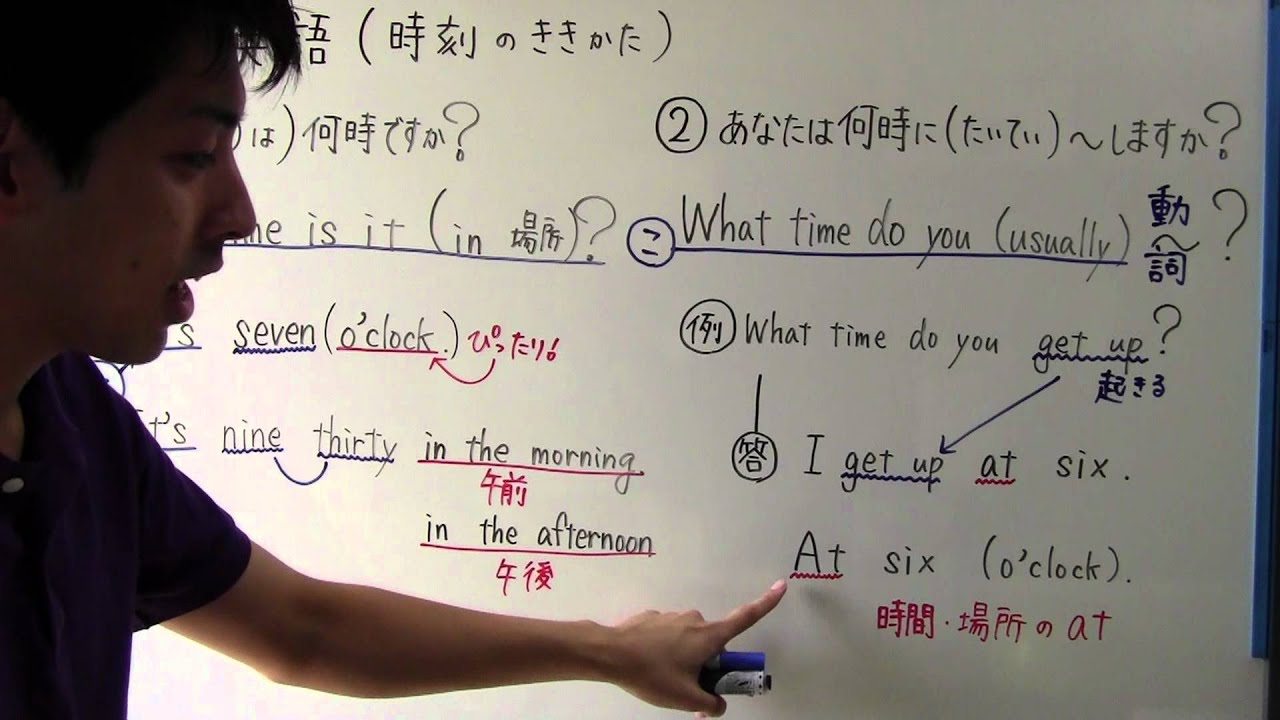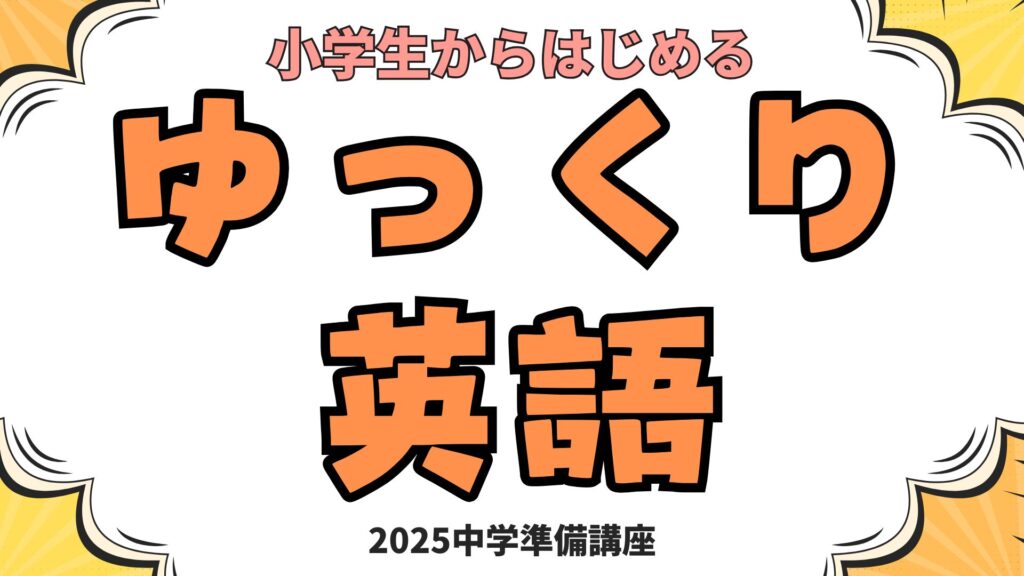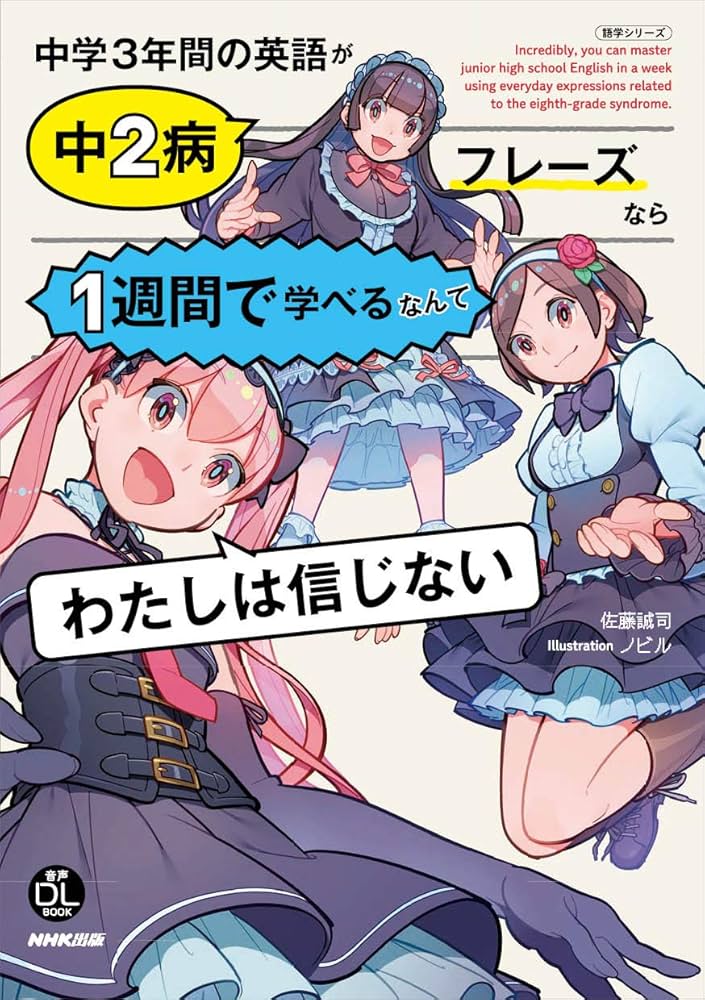<二つの民の土地をめぐる永遠の葛藤>
1948年5月14日、エルサレムの街角でダヴィド・ベン=グリオンがイスラエル独立を宣言した瞬間、ユダヤ人のディアスポラ(離散)の終わりを告げ、2000年にわたる「母国なき民」の夢が現実となりました。しかし、この喜びはパレスチナ人にとっては「ナクバ(大惨事)」の始まり。国連の分割決議でユダヤ国家が認められた一方、パレスチナのアラブ側はこれを拒否し、独立直後の侵攻戦争が勃発しました。 以後、イスラエルとパレスチナの関係は、領土、難民、聖地をめぐる対立として続き、戦争、和平、占領、抵抗のサイクルを繰り返しています。イスラエル側は生存と安全保障を、パレスチナ側は自決権と帰還権を主張し、両者の視点が交錯する中東の核心です。
このブログでは、1948年の建国から2025年9月現在の状況までを時系列で追い、イスラエルとパレスチナの関係を両面から描きます。軍事・外交の出来事だけでなく、経済・社会の側面も交え、共存の可能性を探ります。
<I. 建国とナクバ(大惨事)の影:1948-1967年>
イスラエルの歴史は、独立戦争(パレスチナ側では「ナクバ(大惨事)戦争」)から始まります。1947年の国連パレスチナ分割決議で、ユダヤ国家(イスラエル)とアラブ国家(パレスチナ)が提案されましたが、アラブ側はこれを不平等と拒否。1948年5月15日、エジプト、ヨルダン、シリアらの連合軍が侵攻し、激戦が繰り広げられました。イスラエル側は人口60万人ながら勝利し、国連案より広い領土を確保。1949年の停戦協定で、ヨルダンが西岸と東エルサレムを、エジプトがガザを支配下に置きました。一方、パレスチナ側では70万人の難民が発生し、今日の「パレスチナ難民問題」の基盤となりました。この戦争は、イスラエルにとっては国家誕生の奇跡ですが、パレスチナにとっては故郷喪失の悲劇です。
1950年代、イスラエルは「移民の十年」と称し、ヨーロッパやアラブ諸国から100万人以上のユダヤ人を吸収。キブツ(集団農場)で砂漠を緑化し、経済を急成長させました。しかし、パレスチナ難民の流入を制限し、境界紛争が頻発。1956年のスエズ危機では、イスラエルが英仏と組んでエジプトのシナイ半島を占領しましたが、国際圧力で撤退。パレスチナ側では、PLO(パレスチナ解放機構)の前身がゲリラ活動を始め、抵抗の芽が育ちました。この時期、イスラエル人口は急増する一方、パレスチナ人はヨルダンやレバノンで難民キャンプ生活を強いられ、アイデンティティの危機に直面しました。
1967年の六日戦争は転機。エジプトの軍事動員に対し、イスラエルは先制攻撃で勝利し、シナイ、ガザ、西岸、ゴラン、東エルサレムを占領。イスラエル側は「聖なる勝利」としてエルサレム統一を祝いましたが、パレスチナ側では100万人が占領下に置かれ、抵抗運動が激化。国連安保理決議242号で「土地対平和」の原則が示されましたが、イスラエルは占領地を事実上併合。パレスチナ人の土地没収と入植地建設が始まり、今日の紛争の火種となりました。この戦争後、イスラエル人口は300万人を超えましたが、パレスチナ側はPLOが国際的に台頭し、武装闘争を宣言しました。
<II. 占領と抵抗の時代:1967-1999年>
六日戦争後の占領は、イスラエルとパレスチナの関係を決定的に変えました。1973年のヨム・キプール戦争では、エジプト・シリアの奇襲でイスラエルは苦戦。2700人の死者を出し、「無敵神話」が崩壊しましたが、勝利し領土を維持。パレスチナ側では、PLOが国際テロを展開し、1974年の国連演説で「パレスチナ人の権利」を主張しました。この戦争がきっかけで、1979年のキャンプ・デービッド合意が成立。イスラエルはエジプトにシナイを返還し、初の平和条約を結びましたが、パレスチナ問題は置き去り。サダト大統領の暗殺(1981年)は、エジプト国内の反イスラエル感情を象徴します。
1980年代、レバノン侵攻(1982年)がパレスチナ抵抗を刺激。PLOのロケット攻撃に対し、イスラエルはベイルートを包囲し、サブラ・シャティーラ事件で民間人虐殺が発生。国内反戦デモが起き、1985年に撤退しましたが、ヒズボラの誕生を招きました。パレスチナ側では、1987年の第一次インティファーダ(蜂起)が西岸・ガザで爆発。投石と軍事鎮圧の象徴的な闘争で、国際世論を動かし、イスラエル経済に打撃を与えました。一方、イスラエルでは経済危機をエフード・バラク内閣が改革し、ハイテク産業が芽生えました。
1990年代は希望の光。オスロ合意(1993年)で、ラビン首相とアラファトPLO議長が握手。パレスチナ自治政府(PA)が樹立され、ヨルダンとの平和条約(1994年)も進展。ノーベル平和賞を受賞しましたが、ラビンの暗殺(1995年)で停滞。パレスチナ側では、自治拡大が期待されましたが、入植地拡大が続き、不満が高まりました。1999年の選挙でエフード・バラクが勝利し、シリア交渉を試みましたが失敗。パレスチナの視点では、この時期は「和平の幻想」として記憶され、第二次インティファーダの布石となりました。
<III. テロ、壁、封鎖の連鎖:2000-2019年>
2000年、キャンプ・デービッド会談決裂を機に第二次インティファーダが勃発。自爆テロで1000人以上のイスラエル人が死亡し、シャロン首相は「分離の壁」建設と軍事作戦で対応。パレスチナ側では、4000人以上の死者を出して抵抗しましたが、経済崩壊を招きました。2005年、イスラエルはガザからの一方撤退を実施。入植者撤去は国内分裂を生みましたが、パレスチナ側ではハマスの勝利(2006年選挙)と封鎖の始まりを意味。2006年のレバノン戦争はヒズボラとの激戦で、イスラエルに国際非難を浴びせました。
2000年代後半、ネタニヤフ政権下でガザ作戦(2008-2009年、2012年、2014年)が繰り返され、数千人のパレスチナ死者を出し、国際人権団体から非難。イスラエル経済はハイテクで成長しましたが、パレスチナ側はガザ封鎖で人道危機に。2010年のイラン核問題では、ネタニヤフの「爆弾」演説が注目を集めました。パレスチナの視点では、これらの作戦は「集団懲罰」として記憶されます。
2010年代、外交転機。2018年の米大使館エルサレム移転はパレスチナの「東エルサレム首都」主張を否定し、抗議デモを誘発。2019年のゴラン宣言も同様。和平は停滞しましたが、イスラエル国内ではLGBTQ権利が進展。パレスチナ側では、西岸入植地拡大が続き、2019-2021年の政治危機(5回の選挙)でイスラエルは不安定化。ベネット・ラピド連合がネタニヤフを下しましたが、パレスチナ問題は棚上げされました。
<IV. アブラハム合意とガザの惨劇:2020年代の現在>
2020年、トランプ政権の「アブラハム合意」でUAEらとの正常化が進み、中東地政学を変革。イスラエルはアラブ協力で経済・軍事強化しましたが、パレスチナ側は「裏切り」と非難し、孤立を深めました。2022年のネタニヤフ復帰で右派政権が強化され、司法改革デモが国内を二分。パレスチナでは、西岸での入植者暴力が増加しました。
2023年10月7日、ハマスの大規模攻撃で1200人以上のイスラエル人が殺害、251人が拉致。「鉄の剣」作戦でイスラエルはガザ侵攻、死者数は2025年9月現在、ガザ側66,000人超、イスラエル側数百人に。2023年11月の短期停戦で一部人質解放が進みましたが、戦闘継続。2024年、ヒズボラ・フーシ派の攻撃で北部荒廃、国際司法裁判所で「ジェノサイド」訴訟が発生。パレスチナ側では、ガザのインフラ破壊が深刻で、UN委員会が9月16日にイスラエルをジェノサイドで非難しました。
2025年1月の米仲介停戦合意で人質解放が進みましたが、3月18日の再攻撃でガザで400人以上死亡。9月現在、イスラエルはガザシティを激しく爆撃し、トランプ-ネタニヤフ会談前に57人以上を殺害。米国は21点計画で戦争終了とパレスチナ国家への道筋を提案しましたが、進展なし。ハマスは人質救出のための空爆停止を要請。西岸ではイスラエル行動が拡大し、難民危機が悪化しています。この戦争は、イスラエルに経済打撃を与えつつ、反ユダヤ主義を欧米で増大させ、パレスチナの抵抗を国際化しました。
<Ⅴ.共存への道はまだ遠いが、希望は消えず>
77年の歴史は、イスラエルにとっては生存の闘い、パレスチナにとっては占領と抵抗の物語です。ナクバ(大惨事)からガザの今まで、両者は土地と権利をめぐり血を流しましたが、オスロやアブラハム合意は対話の可能性を示します。2025年9月現在、戦争は続き、死者66,000人超の惨状ですが、米提案の二国家解決が鍵。イスラエルとパレスチナの若者たちが、ハイテクや文化交流で橋を架けられる日を信じましょう。
(参考文献:Al Jazeera、UN、Times of Israelなどに基づく。)
<関連する記事>
<関連する画像>
<関連する動画>
<ツイッターの反応>