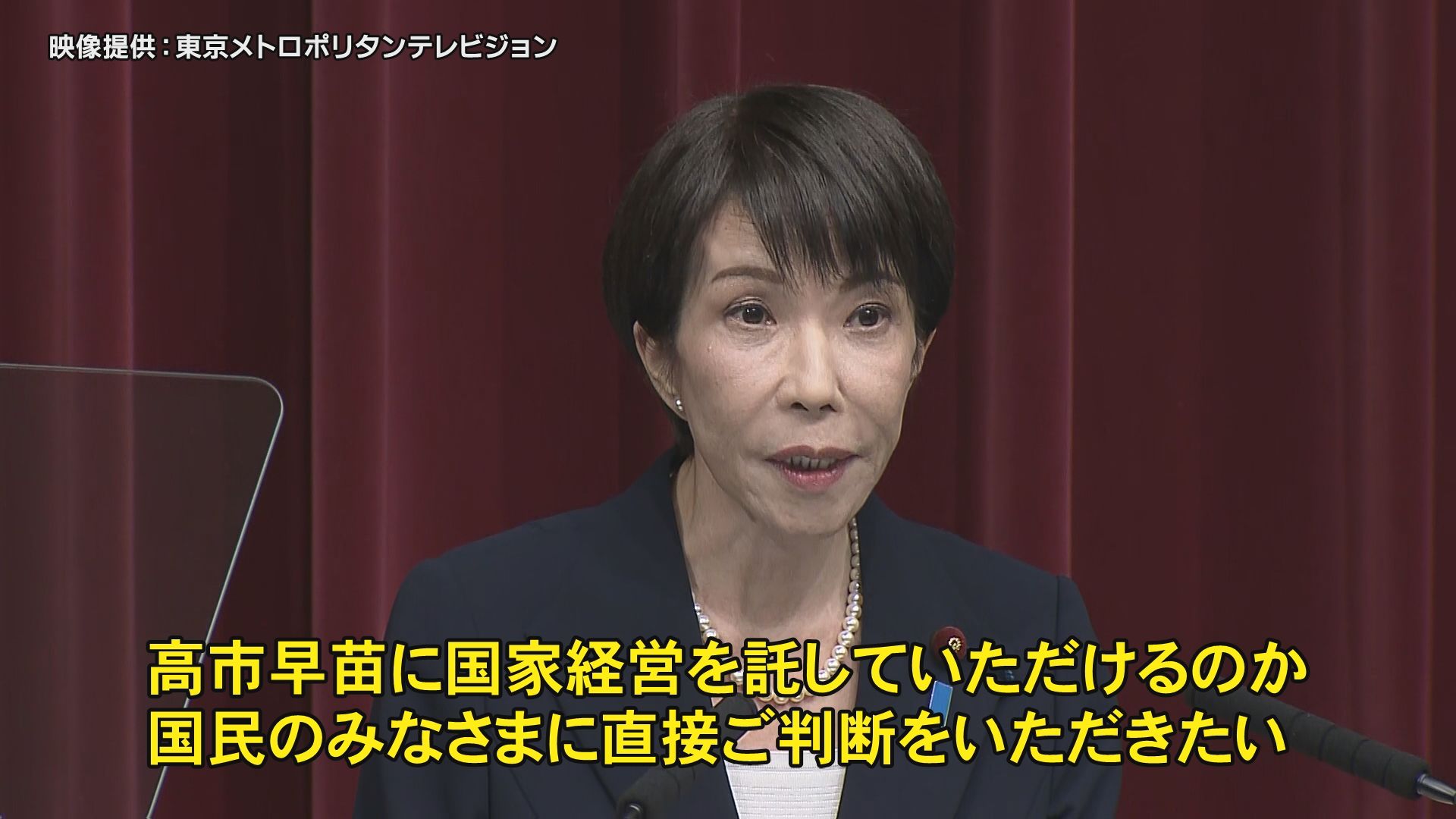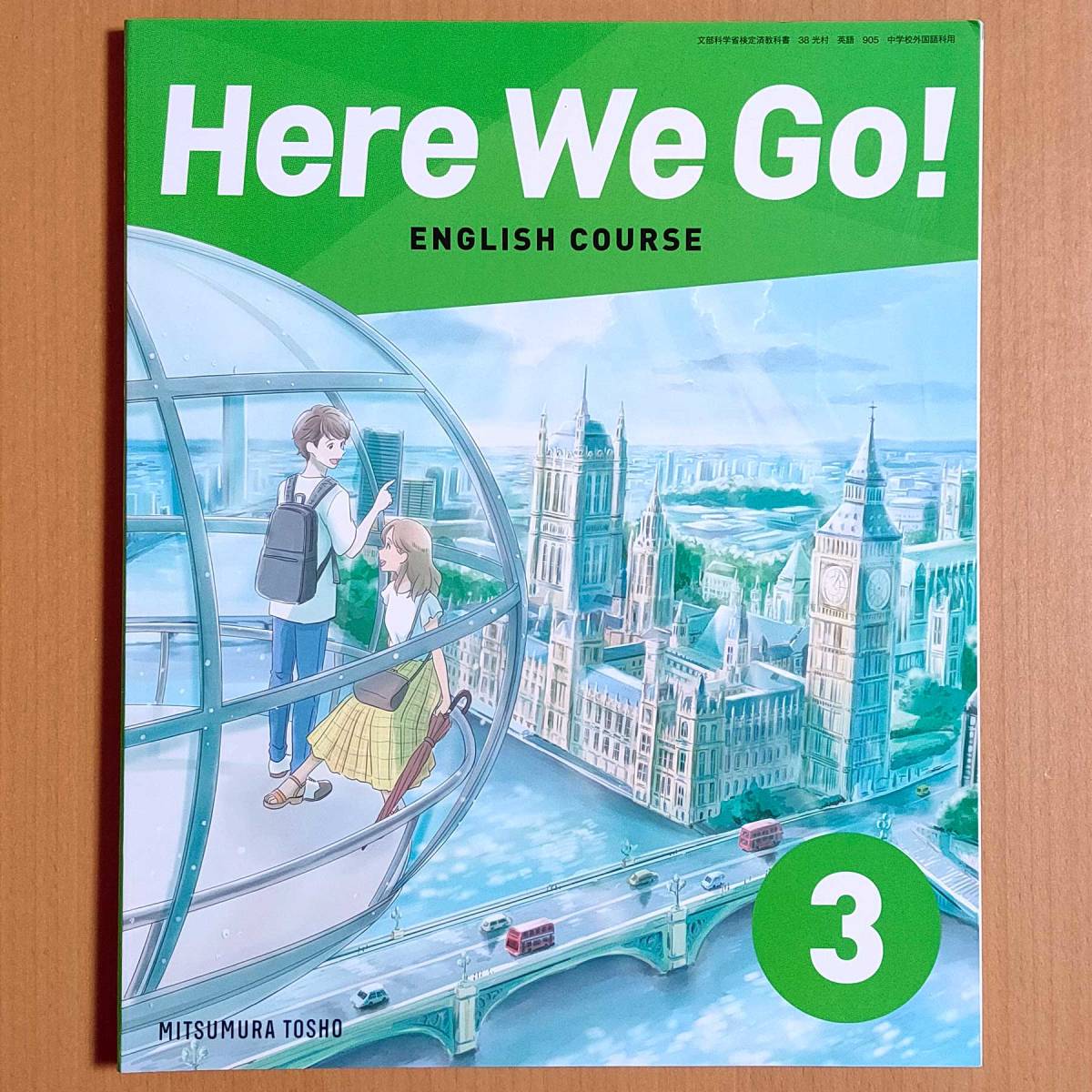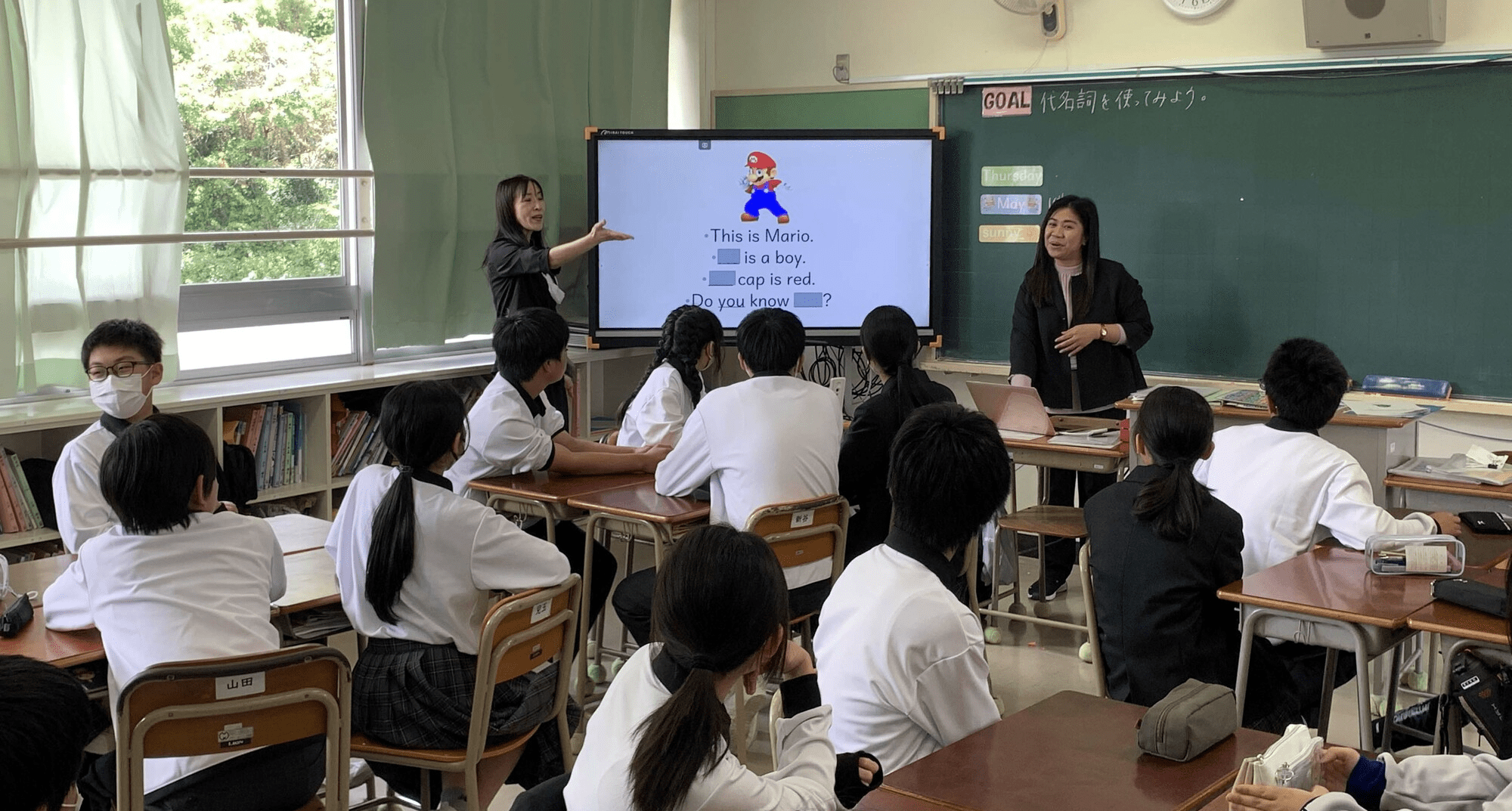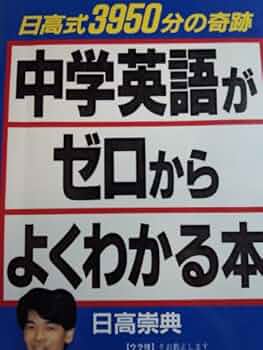故事成語:五里霧中(ごりむちゅう)
故事の概要:
中国の後漢時代に、張楷(ちょうかい)という人物が道術を使って五里(約20km)四方にわたる深い霧を起こし、人々がその中で方角を見失い、混乱に陥ったという故事に由来します。この話は『後漢書』張楷伝に記されています。
慣用句の意味:
物事の事情や方向性が全く見えず、どう行動すればいいかわからない状態。まるで五里もの深い霧の中にいるような様子を表します。
補足:
「五里」とは古代中国の距離単位で、約2km(現代の1里の約2.5倍)なので、五里は約10km前後を指しますが、比喩的に広大な霧のイメージを強調しています。主に状況の不明瞭さを表現する際に使われます。
使用例:
・このプロジェクトの進捗が全く見えず、五里霧中だ。
・霧雨が激しくなり、運転手は五里霧中となって道に迷った。
類義語:
・暗中模索(あんちゅうもさく):手探りで進む様子。
・藪の中(やぶのうち):事情が複雑でわからない状態。
・迷走(めいそう):方向を見失って彷徨う様子。
<関連する記事>
<関連する画像>
<ツイッターの反応>
Visited 28 times, 2 visit(s) today